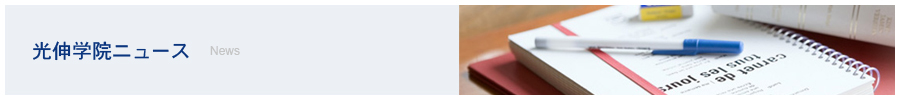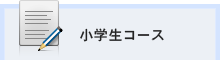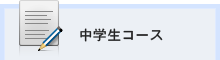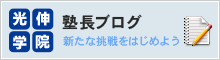都立高校最終応募倍率
春を感じさせる陽気も見られるようになりました。 2月もあと少し。
14日(水)に都立出願の取下げ、15日(木)に再提出が行われ、
各校の最終応募倍率が出ました。
コース制や単位制を除く、普通科男子は1.54(前年比-0.03)、
女子は1.57(前年比-0.01)で合計1.55(前年比-0.03)でした。
また、普通科コース制は1.34(前年比-0.28)、単位制は1.37(前年比-0.16)で、
普通科合計は1.52(前年比-0.03)となりました。
専門学科は1.13(前年比-0.19)、総合学科は1.20(前年比-0.20)となり、
全日制合計は1.44(前年比-0.06)でした。
全体的に、倍率は低下傾向となりました。 特に専門学科は定員割れも多く、
商業科は全体としても0.98(前年比-0.18)と、割れた状態に終わりました。
ただ、やはり人気校は高倍率のままで、普通科男子は戸山高校(2.39)、
女子は広尾高校(2.43)がトップです。 単位制では、新宿高校が人気で2.31、
そして人気の国際高校は2.99でした。 他にも2倍を超える人気校も多く、
厳しい戦いは続きそうです。
さて、泣いても笑っても都立高校一般入試まで1週間!
できることを全てやるしかないな、ということで、今年も子供たちと共に、頑張ります!
齋藤 |
都立高校応募倍率(初日)が発表されました
昨日、都立高校の出願があり、初日の応募倍率が出ました。
全日制普通科は、男子1.54、女子1.57とどちらも前年比-0.01で、
男女計1.55でこちらも前年比-0.01でした。 以下、
コース制: 1.34(前年比-0.24)
単位制 : 1.33(前年比-0.19)
普通科合計: 1.51(前年比-0.03)
専門学科計: 1.09(前年比-0.20)
総合学科計: 1.14(前年比-0.23)
全日制合計: 1.42(前年比-0.07)
となっています。
全体的に見ると、前年よりも緩やかな傾向がありますが、2倍を超える高校も
少なくなく、人気校は厳しい戦いになりそうです。
男子は戸山高校が2.48、女子は広尾高校が2.51でトップでした。
広尾の人気は今年も変わりませんね。 そして、国際高校の倍率も相変らず高く、
今年は3.16でした。
今日も出願を受け付けており、多少の変化があるとは思いますが、大勢は決まりました。
来週は取下げと再提出が行われ、最終応募倍率はそこで確定します。
兎にも角にも、残り2週間ちょっと。 できることをすべて頑張っていこうと思います。
齋藤 |
新学年のクラス状況とキャンペーンお知らせ
良い天気が続いています。
今日は都立高校の出願日です。 いよいよ今年もやってきたな、という感じです。
2月は受験・定期テストと続きますが、3月からは新たな学年としてのスタートです。
毎年、塾では「新学年スタートキャンペーン」として、3月を丸々体験できるように
しています。 前半は無料体験、後半(春の講習を含む)は有料体験で、4月からの
正式入塾を検討して頂く機会を設けています。
そこで、塾の新学年状況を。
小学生コース: 現小6生が中学生コースへ移行するため、各曜日余裕あります
新中学1年生: 申し訳ございません。 ほぼ定員で、満員です。
新中学2年生: 定員まで5名です。
新中学3年生: 定員まで6名です。
今月より、この新学年スタートキャンペーンへの予約を受け付けております。
中学生コースご希望の方は、2月中のご予約による特典もございます。
新中1生は、フォニックス英語指導を、新中2、中3生は定期テスト対策を
2月後半からご参加可能です。
是非、この機会をご利用下さい。
詳細はご遠慮なくお問い合わせ下さい。
齋藤
|
定期テスト3週前になりました
それにしても、今年の冬は寒いですね。
2月5日になりました。 学校の定期テストまで3週間です。
提出物になりそうなワーク類等、そろそろ始めておくとテスト前が
楽になりますね。
特に、冬休みの宿題として課題がなかったワークは、
前回の範囲終わりから考えると、大量の課題が出る可能性も
あります。
テスト1週間前に提出物を終わらせるのが理想です。
塾でも、先週くらいから声を掛け始めています。
3年生の受験シーズンですが、1,2年生の定期テストもしっかりと。
一緒に頑張ります!
齋藤
|
何の先生?(ブログより)
寒い日が続いていますね。
「塾の講師をしています」と言うと、大抵の人に「何の先生?」と聞かれます。
特に専門のない私は、「う~ん、理科以外かな」と以前は答えていました。
そもそも、「英語なら教えられるかな?」という気持ちでこの業界に入りましたが、
最初に勤めた塾で、「理科以外」を教えるという状況だったので。
そこの塾長先生が「理科はやはり理系の方に」という考えで、それ以外はやりましょう~
というスタイルでした。 そして、英語系の方が多くなる中で、数学に傾いていくこと
になりました。
次の塾でも、理系でもないのに「数学科」を希望し、現場では「理科以外」
を教えていました。
自分で塾を開くことになって、一番の懸念はこの「理科」でした。 塾歴はあるものの、
「理科は人任せ」でしたから。 しかし、そうも言ってられません。 映像授業ではあるものの、
そのフォローは必須です。
そうしているうちに、ようやく受験理科も何とかなるようになり、理科の授業もできるかな、
にはなりました。 年を重ねても、成長はするもんだな…なんて思ったりします。
オールマイティと言えば聞こえは良いものの、自分の中では「専門がない」
という気もしています。 「何の先生?」に対しても、どう答えるべきか。
最近は「塾の先生」でいいのかな、とも思い始めています。 ただ、自分ではあまり
「先生」という感覚を持っていなくて、塾を始める時から「色々教えてくれる近所のおっさん」
的な存在でいいかな、と思っています。
これからも、人に聞かれたら「塾の先生」。 気持ちは「何でも教える近所のおっさん」で。
そんなことを考えています。
齋藤
|